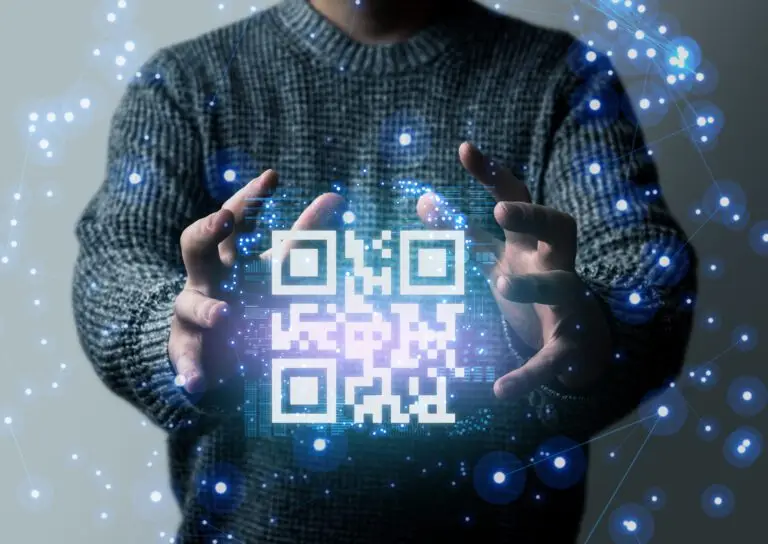お墓じまいとは
墓を建てている土地は、墓地・霊園・寺院などの運営者の所有地となるため、墓の購入者には土地の所有権はありません。つまり、土地を借用している(使用権を購入している)に過ぎないのです。
墓じまいとは、今あるお墓の管理・維持が困難になり、ご遺骨を新しい場所に移すために、墓石を解体・撤去し、更地にして管理者(寺、運営会社、自治体)に使用権を返還することを指します。


墓じまいの流れ
墓じまいをするには、以下の7ステップの流れで手続きを進めていきます。
- 親族の同意を得る:墓じまいを行うためには、親族の同意が基本的に必要です。(後でのもめごとにならないように)
- 改葬先を決める:墓じまいの後は、ご遺骨を新しい場所に移さなければなりません。改葬先としては、別の墓地や霊園、永代供養墓地、散骨などが挙げられます。
- 墓地の管理者に連絡する:墓じまいをする場合は、墓地の管理者に連絡し、手続きの説明を受けます。
- 改葬許可証を取得する:改葬先に納骨するためには、「改葬許可証」が必要です。市区町村の役所で取得できます。
- 遺骨を取り出す:改葬許可証を取得したら、墓石を撤去し、遺骨を取り出します。遺骨の取り出しは、石材店などに依頼するのが一般的です。
- 墓石を撤去する:遺骨を取り出したら、墓石を撤去します。墓石の撤去も、石材店などに依頼するのが一般的です。
- 改葬先に納骨する:墓石を撤去したら、改葬先に納骨します。※ 霊園から『受入証明書』を入手が必要な場合もあり。
墓じまいの費用
墓じまいの費用は、一般的には、30万円〜200万円程度かかると言われています。費用を抑えるためには、改葬先を慎重に選び、墓石の撤去や納骨を自分で行うなどの方法があります。
移転先の選択肢(費用順)
墓じまいを検討する際には、納骨先を選ぶ必要があります。改葬先には、以下のようなものがあります。(お墓の種類と費用相場)
- 樹木葬:70万円程度
- 納骨堂:50万円程度
- 合同墓:10~30万円程度
- 散骨:20~30万円程度
- 自宅墓:5千円~20万円程度
※移転先は、お墓じまいの費用の削減の重要なポイントです。
永代供養墓とは
永代供養墓は、お墓の管理や供養を寺院や霊園が永久に行うことを条件に、遺骨を安置する墓地のことです。近年、墓じまいを検討する際に、永代供養墓を選ぶ方が増えています。
永代供養墓は、一般的に以下のようなメリットがあります。
- 墓地や霊園の管理費や供養料が永久に不要
- 墓石の管理や修繕などの手間がかからな
- 法要やお参りなどの手間が省ける
しかし、永代供養墓には、以下のようなデメリットもあります。
- 永代供養墓の規定期間が設けられている場合があり、その期間が経過すると、遺骨が合祀される
- 供養塔・合祀墓の永代供養では、遺骨を取り出すことができない
- 先祖史が絶える可能性がある
永代供養墓を選ぶ際には、これらのメリットとデメリットをよく理解したうえで、ご家族でよく話し合って決めましょう。

まとめ
墓じまいは、お墓を撤去し、遺骨を新しい場所に移すことです。近年、少子高齢化や核家族化、ライフスタイルの変化などにより、墓じまいを検討する方が増えています。
墓じまいの費用は、30万円〜200万円程度が相場です。費用の内訳としては、改葬許可証の取得費用、遺骨の取り出し費用、墓石の撤去費用、改葬先の費用などが挙げられます。墓じまいの移転先としては、樹木葬、納骨堂、合同墓、散骨、自宅墓などがあります。費用や供養方法などを考慮して、ご家族でよく話し合って決めましょう。
近年、墓じまいは、様々なニーズに合わせて、新しい形へと変わってきています。墓じまいを検討する際には、移転先の多様化や、墓じまいの意義を理解した上で、ご家族でよく話し合って決めましょう。